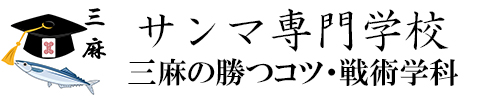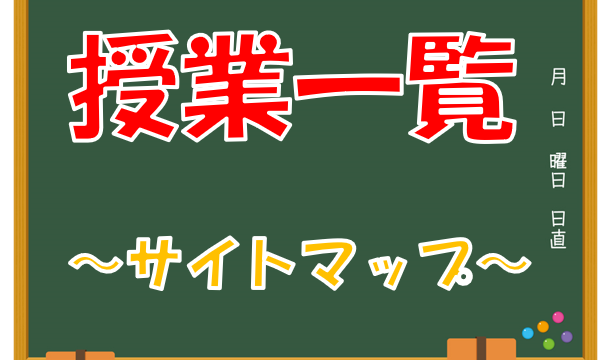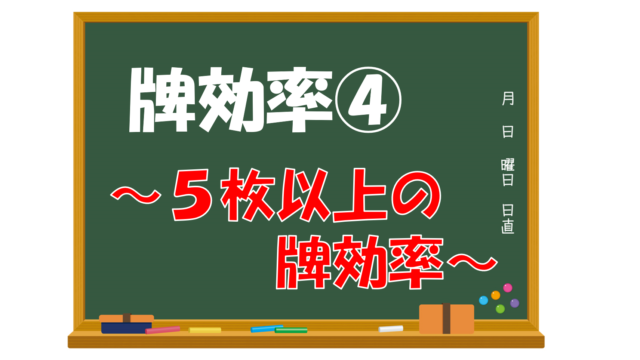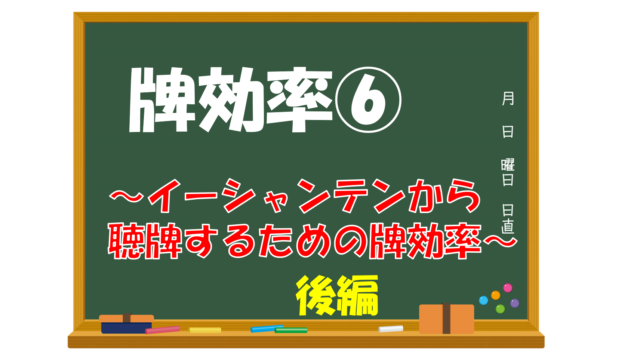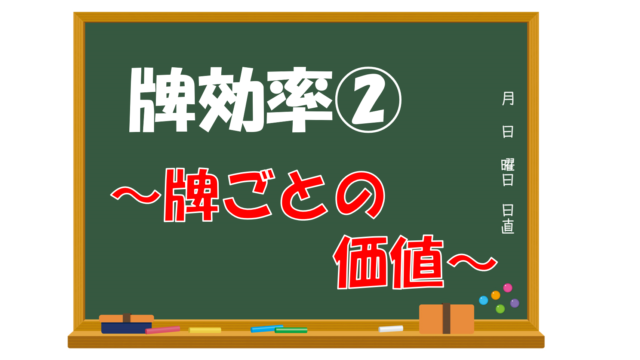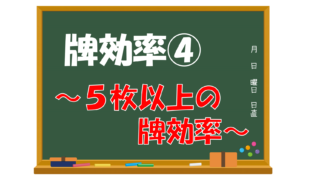前回までで、塔子・1枚ごと・3枚形や4枚形・5枚以上の牌効率を学んできました。
最終的には如何に効率よく聴牌してアガるかのための牌効率です。より実戦的にイーシャンテンから聴牌するための牌効率を解説します!
聴牌がいかに偉いか
まず、イーシャンテン(一向聴=聴牌の一歩手前)や聴牌と比べてもアガルことが一番偉く価値が高いのは当たり前ですが、「イーシャンテン」と「聴牌」でも大きな価値の差があることを理解してください。
それは何故か。
イーシャンテンまでは(鳴かない限りは)自分で有効牌をツモってこなければなりません。
また、鳴くことができても、鳴いた上でちゃんとアガれる手牌じゃないといけません。
一方聴牌していると、役がある限り、自分のツモだけではなくて相手の捨て牌でロンアガリできますよね。
感覚でより分かってもらうために、例で説明します。
子が先制で![]()
![]() 待ちの両面のリーチをしているとします。親が筒子の清一色のイーシャンテンだとします。
待ちの両面のリーチをしているとします。親が筒子の清一色のイーシャンテンだとします。
筒子の何引いても聴牌しそうな受け入れの広いイーシャンテンです。
親も勝負したいのはやまやまですが、ここから危険牌も捨てて勝負しても、聴牌してアガリになる前に![]()
![]() を持ってきてしまえば、親の清一色のアガリができなくなるのはもちろん、アガリも厳しく振り込みか降りるしかほぼありません。
を持ってきてしまえば、親の清一色のアガリができなくなるのはもちろん、アガリも厳しく振り込みか降りるしかほぼありません。
一方で先制リーチした子は親の欲しい筒子を持ってきても現状ロンされることはありません。
自分がアガリ牌をツモっても良し、勝負してきた子が振り込んでくれても良しの有利な状態です。
長くなりましたが、聴牌者がそれ以外の人たちと比べて大きなアドバンテージを得ているのを理解してもられたのではないかと思います。
イーシャンテンからいかに聴牌する確率をあげるか
イーシャンテンからなかなか聴牌しないことよくありますよね。
イーシャンテンまではすんなり来たのに…。
もちろんたまたまということもありますが、イーシャンテンまで進む確率とイーシャンテンから聴牌する確率では、後者の方が少ないのです。
それは聴牌に近くにつれて受け入れ牌が減るからです。
また聴牌すれば一番受け入れが狭くなります。
例えばリャンシャンテン(二向聴=イーシャンテンの一歩手前)から見てみましょう。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
イーシャンテンに進む受け入れ牌は![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の5種20牌です。
の5種20牌です。
ここで![]() が来て
が来て![]() を切ったとします。
を切ったとします。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
続いて聴牌する受け入れ牌は![]()
![]()
![]() の3種12牌です。
の3種12牌です。
ここで![]() が来て
が来て![]() を切ったとします。先ほどのイーシャンテン時と比べて、減ってますよね。
を切ったとします。先ほどのイーシャンテン時と比べて、減ってますよね。
次に![]() が来て
が来て![]() を切ったとします。
を切ったとします。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
これで聴牌ですね。
受け入れ牌=アガリ牌は![]()
![]() の2種8牌です。
の2種8牌です。
ご覧いただいた様に、有効牌が来て、面子や頭ができて手牌が進行する度に有効牌の種類と数が減っていきます。
では聴牌からアガルのが一番確率が低いのかというとそうではありません。
前項のように聴牌していれば他家の捨て牌からロンアガリできるが、聴牌までは自分のツモ牌頼みです。ですので、基本はイーシャンテンから聴牌までが一番大変なのです。
ただ、「該当の牌が対子以上に限られること」「ポンして役を確保できるのか」等の条件が揃えば、相手の捨て牌を「ポン」して利用することができますね。
上記のようにイーシャンテンから聴牌へ移行するのがとても重要でかつ大変なために、イーシャンテン時の受け入れを最大限高めようという考え方を「イーシャンテンピーク理論」と言います。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
上の例のイーシャンテン時の手牌に![]() をツモってきたところです。
をツモってきたところです。
![]() を切ると聴牌する受け入れ牌は
を切ると聴牌する受け入れ牌は![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の5種16牌です。
の5種16牌です。![]()
![]() の2種4牌が増えましたね。
の2種4牌が増えましたね。
ここで常に![]() をツモ切ってしまう人もいると思いますし、ツモ切るべき状況もあると思います。
をツモ切ってしまう人もいると思いますし、ツモ切るべき状況もあると思います。
しかし4枚の受け入れの差はイーシャンテンから聴牌する難しさを考えると十分価値があると言えます。
この受け入れ枚数をより大きくするのが「イーシャンテンピーク理論」です。
ただ![]() が2枚捨てらている等あれば
が2枚捨てらている等あれば![]() よりも安全度の高い
よりも安全度の高い![]() を持っておく比重も多くなるのでケースバイケースと言えます。
を持っておく比重も多くなるのでケースバイケースと言えます。
特に3人全員聴牌も当たり前の三麻では、聴牌した際の余り牌が危険牌となりうる場合は、多少の受け入れを減らしてでも、先切りすることも少なくありません。
完全イーシャンテン
「完全イーシャンテン」というものを覚えていただきます。上記の![]() を
を![]() に変えました。
に変えました。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
これで![]() を切ると「完全イーシャンテン」になります。
を切ると「完全イーシャンテン」になります。
何が「完全イーシャンテン」かというと、聴牌する受け入れ牌は(![]()
![]() の両面)+(
の両面)+(![]()
![]() の両面)+(
の両面)+(![]()
![]() のシャンポン)になってますよね。
のシャンポン)になってますよね。
この両面+両面+シャンポンの受け入れのイーシャンテンを「完全イーシャンテン」と言います。
また、何が入っても両面待ちのリーチが打てますね。
ただ完全イーシャンテンという名前ですが、イーシャンテンの中ではもっと受け入れの広いパターンがあります。
まとめ
- イーシャンテンより聴牌の方が大きなアドバンテージがある
- イーシャンテンから聴牌にするのが一番大変
- イーシャンテンピーク理論は大事だが、安全度の高い牌を抱えることも必要になる。
前半のまとめはこんな感じです。次の後半では単純にイーシャンテンでどんな形があるか見ていきます。
後半の記事はこちらです↓
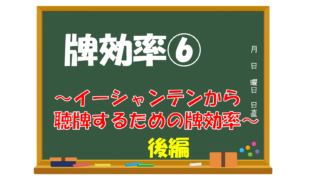
是非他の記事も見ていってください。ありがとうございました!
このブログの他にも、三人麻雀オンラインゲーム「雀魂」をプレイしたときの牌譜から勉強になりそうなものをピックアップして記事を書いています。
一打ごとの選択理由など細かく記載していますので、初・中級者の方にとっては貴重な記事になるはずです。
有料のものもありますが缶ジュース程度の金額ですので、強くなりたい方は是非覗いてみてください!